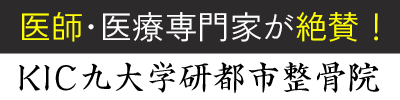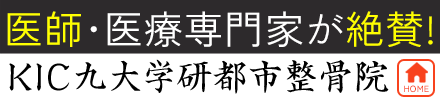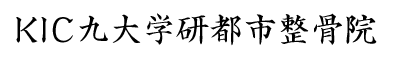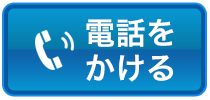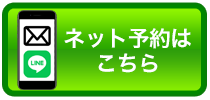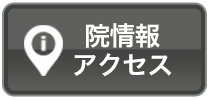【目次】
1. 顎関節症は“女性”に多い
2. 顎関節症は“あご以外”の症状を引き起こす
3. 精神的ストレスが大きく関与する
4. 噛み合わせのズレは「原因」ではなく「結果」のこともある
5. 睡眠中の癖が症状を悪化させる
6. 子どもや高齢者にも見られる
7. 運動や姿勢とも関係している
8. 症状が自然に改善することもある
顎関節症と聞くと、多くの人が「あごの関節が痛む」「口が開けづらい」といった典型的な症状を思い浮かべるでしょう。
しかし、顎関節症は単に顎の関節や筋肉に起きる局所的な障害にとどまらず、全身の健康や精神状態、さらには日常生活の質にも深く関わることが、近年の研究や臨床経験から明らかになってきました。
ここでは、あまり知られていない「顎関節症の意外な事実」について、いくつかの観点から詳しく紹介していきます。
 1. 顎関節症は“女性”に多い
顎関節症の患者の約7割が女性であることが、複数の疫学調査で示されています。
特に20~40代の女性に多く見られるのが特徴です。
その理由は完全には解明されていませんが、ホルモンの影響が一因と考えられています。女性ホルモンであるエストロゲンには、関節や靱帯の柔軟性に関わる作用があるとされ、これが関節の安定性を損ないやすくする可能性があります。
また、女性の方がストレスに敏感であるという心理的傾向も、筋緊張や食いしばりを引き起こしやすく、顎関節症のリスクを高める要因と考えられています。
2. 顎関節症は“あご以外”の症状を引き起こす
顎関節症は、実はあご周辺以外のさまざまな部位にも症状をもたらすことがあります。
代表的なのは頭痛、首こり、肩こり、背中の痛みなどで、特に筋肉由来の症状が多く報告されています。
これらは、咀嚼筋と呼ばれるあごの筋肉群が過緊張を起こし、それが頭部や頸部の筋肉へ連鎖的に負担をかけることによって引き起こされます。
また、三叉神経や顔面神経といった、顔面に広がる神経を介して、目の奥の痛み、耳の閉塞感、めまいなどが出現することもあります。
3. 精神的ストレスが大きく関与する
顎関節症と聞くと、物理的な噛み合わせや顎の使い方が原因と思われがちですが、実際にはストレスや不安、抑うつといった心理的要因が深く関与していることが多くあります。ストレスが高まると、無意識のうちに「食いしばり」や「歯ぎしり」をするようになり、それが顎の筋肉や関節に大きな負担をかけて症状を悪化させます。
また、長期間にわたって顎関節症に悩まされること自体がストレスとなり、症状を慢性化させるという悪循環に陥ることもあります。
4. 噛み合わせのズレは「原因」ではなく「結果」のこともある
かつては、顎関節症の主な原因は「不正咬合(かみあわせの悪さ)」だと考えられていました。
しかし、近年ではこの見解は見直されつつあります。
実際には、噛み合わせのズレが顎関節症の「結果」として現れることも多いのです。
例えば、慢性的な食いしばりや筋肉の過緊張が続くことで、下顎の位置が変化し、結果として噛み合わせが乱れてくるというメカニズムです。
したがって、ただ単に噛み合わせを調整するだけでは根本的な解決にならない場合が多く、筋肉や関節、生活習慣への包括的なアプローチが重要です。
1. 顎関節症は“女性”に多い
顎関節症の患者の約7割が女性であることが、複数の疫学調査で示されています。
特に20~40代の女性に多く見られるのが特徴です。
その理由は完全には解明されていませんが、ホルモンの影響が一因と考えられています。女性ホルモンであるエストロゲンには、関節や靱帯の柔軟性に関わる作用があるとされ、これが関節の安定性を損ないやすくする可能性があります。
また、女性の方がストレスに敏感であるという心理的傾向も、筋緊張や食いしばりを引き起こしやすく、顎関節症のリスクを高める要因と考えられています。
2. 顎関節症は“あご以外”の症状を引き起こす
顎関節症は、実はあご周辺以外のさまざまな部位にも症状をもたらすことがあります。
代表的なのは頭痛、首こり、肩こり、背中の痛みなどで、特に筋肉由来の症状が多く報告されています。
これらは、咀嚼筋と呼ばれるあごの筋肉群が過緊張を起こし、それが頭部や頸部の筋肉へ連鎖的に負担をかけることによって引き起こされます。
また、三叉神経や顔面神経といった、顔面に広がる神経を介して、目の奥の痛み、耳の閉塞感、めまいなどが出現することもあります。
3. 精神的ストレスが大きく関与する
顎関節症と聞くと、物理的な噛み合わせや顎の使い方が原因と思われがちですが、実際にはストレスや不安、抑うつといった心理的要因が深く関与していることが多くあります。ストレスが高まると、無意識のうちに「食いしばり」や「歯ぎしり」をするようになり、それが顎の筋肉や関節に大きな負担をかけて症状を悪化させます。
また、長期間にわたって顎関節症に悩まされること自体がストレスとなり、症状を慢性化させるという悪循環に陥ることもあります。
4. 噛み合わせのズレは「原因」ではなく「結果」のこともある
かつては、顎関節症の主な原因は「不正咬合(かみあわせの悪さ)」だと考えられていました。
しかし、近年ではこの見解は見直されつつあります。
実際には、噛み合わせのズレが顎関節症の「結果」として現れることも多いのです。
例えば、慢性的な食いしばりや筋肉の過緊張が続くことで、下顎の位置が変化し、結果として噛み合わせが乱れてくるというメカニズムです。
したがって、ただ単に噛み合わせを調整するだけでは根本的な解決にならない場合が多く、筋肉や関節、生活習慣への包括的なアプローチが重要です。
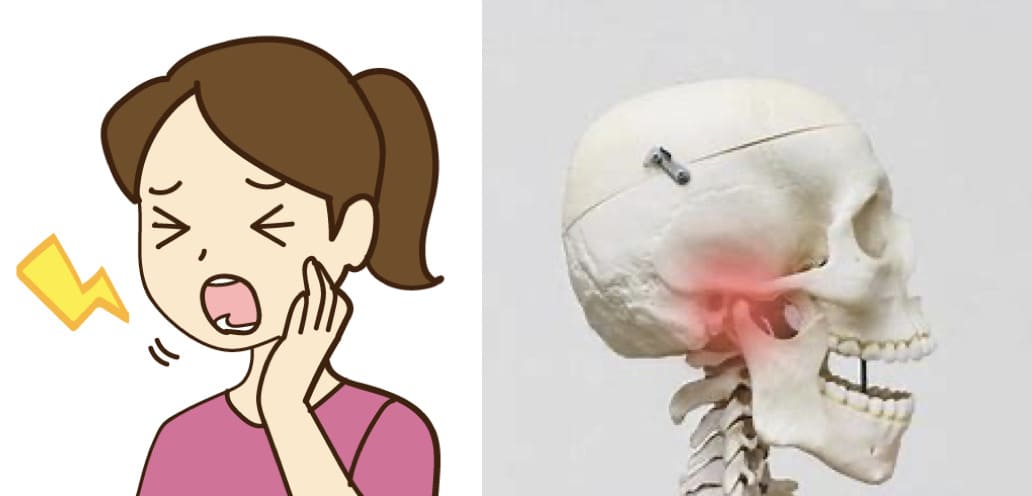 5. 睡眠中の癖が症状を悪化させる
寝ている間に無意識に歯ぎしりをしたり、横向きやうつ伏せで寝る癖があると、顎関節に大きな負担がかかり、症状が悪化することがあります。
特に歯ぎしりは、起きている間にかかる咬合力の2倍以上の力がかかるとされ、関節や筋肉に慢性的なダメージを与えます。
しかも、本人はその習慣に気づかないことが多いため、症状が進行するまで見過ごされがちです。
マウスピースの使用や、寝姿勢の見直し、リラックス法の導入などが予防につながります。
6. 子どもや高齢者にも見られる
顎関節症は若い女性に多いとされますが、実は子どもや高齢者にも発症します。
子どもの場合、骨の発育に伴って一時的に顎関節に負担がかかることや、ストレスによる癖(頬杖や爪かみなど)が原因になることがあります。
一方で高齢者では、長年の咀嚼習慣や歯の喪失、入れ歯の不適合などが影響して、顎関節のバランスが崩れることがあります。
いずれの場合も、年齢に応じた対処法が必要です。
7. 運動や姿勢とも関係している
顎関節の動きは、首や肩、背骨の動きとも密接に関係しています。
特に「猫背」や「頭が前に出る姿勢」は、下顎の位置を不安定にし、関節や筋肉に負担をかけやすくします。
また、首まわりの筋肉が硬くなることで、顎関節の動きが制限されることも考えられます。
したがって、正しい姿勢や全身のバランスを意識することが、顎関節症の予防・改善に大きく役立ちます。
8. 症状が自然に改善することもある
意外にも顎関節症の多くは、時間の経過とともに自然に改善するケースもあります。
実際、軽度の症状であれば、特別な治療を行わなくても、ストレスの軽減や生活習慣の改善によって徐々に良くなっていく場合があります。
とはいえ、強い痛みや長引く症状がある場合は、早めに専門医に相談することが大切です。
まとめ
顎関節症は単なる「あごの病気」ではなく、身体全体のバランスや精神状態、生活習慣とも深く関係しています。
その症状や原因は非常に多様で、思わぬところに影響を及ぼすことも少なくありません。こうした「意外な事実」を知ることで、自分の症状の理解が深まり、より効果的な対策をとることができるようになります。
顎関節症を単なる局所的な不調として捉えるのではなく、全身の健康の一部として捉え、日々の生活の中でできることから取り組んでいくことが、改善への第一歩となるでしょう。
KIC九大学研都市整骨院では顎関節症の原因を究明し、根本的に改善に導きます。
顎の痛みや違和感など何かお身体の事でお困りでしたら当院までお気軽にご相談下さい。
5. 睡眠中の癖が症状を悪化させる
寝ている間に無意識に歯ぎしりをしたり、横向きやうつ伏せで寝る癖があると、顎関節に大きな負担がかかり、症状が悪化することがあります。
特に歯ぎしりは、起きている間にかかる咬合力の2倍以上の力がかかるとされ、関節や筋肉に慢性的なダメージを与えます。
しかも、本人はその習慣に気づかないことが多いため、症状が進行するまで見過ごされがちです。
マウスピースの使用や、寝姿勢の見直し、リラックス法の導入などが予防につながります。
6. 子どもや高齢者にも見られる
顎関節症は若い女性に多いとされますが、実は子どもや高齢者にも発症します。
子どもの場合、骨の発育に伴って一時的に顎関節に負担がかかることや、ストレスによる癖(頬杖や爪かみなど)が原因になることがあります。
一方で高齢者では、長年の咀嚼習慣や歯の喪失、入れ歯の不適合などが影響して、顎関節のバランスが崩れることがあります。
いずれの場合も、年齢に応じた対処法が必要です。
7. 運動や姿勢とも関係している
顎関節の動きは、首や肩、背骨の動きとも密接に関係しています。
特に「猫背」や「頭が前に出る姿勢」は、下顎の位置を不安定にし、関節や筋肉に負担をかけやすくします。
また、首まわりの筋肉が硬くなることで、顎関節の動きが制限されることも考えられます。
したがって、正しい姿勢や全身のバランスを意識することが、顎関節症の予防・改善に大きく役立ちます。
8. 症状が自然に改善することもある
意外にも顎関節症の多くは、時間の経過とともに自然に改善するケースもあります。
実際、軽度の症状であれば、特別な治療を行わなくても、ストレスの軽減や生活習慣の改善によって徐々に良くなっていく場合があります。
とはいえ、強い痛みや長引く症状がある場合は、早めに専門医に相談することが大切です。
まとめ
顎関節症は単なる「あごの病気」ではなく、身体全体のバランスや精神状態、生活習慣とも深く関係しています。
その症状や原因は非常に多様で、思わぬところに影響を及ぼすことも少なくありません。こうした「意外な事実」を知ることで、自分の症状の理解が深まり、より効果的な対策をとることができるようになります。
顎関節症を単なる局所的な不調として捉えるのではなく、全身の健康の一部として捉え、日々の生活の中でできることから取り組んでいくことが、改善への第一歩となるでしょう。
KIC九大学研都市整骨院では顎関節症の原因を究明し、根本的に改善に導きます。
顎の痛みや違和感など何かお身体の事でお困りでしたら当院までお気軽にご相談下さい。
【福岡市にある当院のホームページはこちらから】 https://kic-momochi-seikotsuin.com/
【顎関節症はこちらから】https://kic-momochi-seikotsuin.com/gaku-kansetsu/
【LINE】 https://lin.ee/mzts765 LINEでの問い合わせ、ご予約も可能です
<関連記事はこちら>